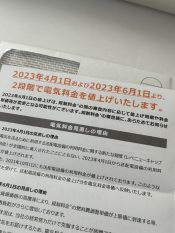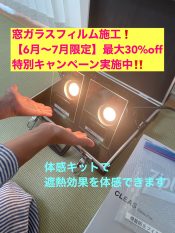防犯フィルムは意味ない?本当の効果と最強の防犯対策を徹底解説!
防犯フィルムは意味ないと言われることがありますが、実は適切に選び正しく施工すれば、防犯効果はしっかり発揮されます。
「防犯フィルムを貼ったのに窓ガラスを破られてしまった」「結局のところ、意味ないんじゃないの?」という声も耳にしますが、こうした失敗のほとんどは、フィルム選びや施工方法に問題があるケースが多いのです。
そこでこの記事では、防犯フィルムが意味ないと言われる原因を探り、防犯効果をしっかり発揮させるための選び方や施工のポイントを詳しく解説します。
また、防犯効果が認められた「CPマーク」付き防犯フィルムの特徴や、自分で施工する際の注意点、ホームセンターで購入する時のポイントまで徹底解説します。
さらに、防犯フィルムと防犯ガラスの違いや施工価格の目安もまとめましたので、ぜひ最後までご覧くださいね。
目次
防犯フィルムは意味ないって本当?
防犯フィルムは「意味ない」といった声が聞かれることがありますが、実際にはきちんとした効果が認められています。
そもそも防犯フィルムとは、窓ガラスに貼ることで、ガラスを割られにくくする目的で作られた透明フィルムのことを指します。割れたとしてもガラスが簡単に破片になって散らばらないため、空き巣や不審者が侵入するまでの時間を引き延ばすことが可能です。これは空き巣などの侵入犯に対する重要な防犯対策になります。
それでは、なぜ「防犯フィルムは意味ない」と感じてしまう人がいるのでしょうか?主な理由は、以下のようなものがあります。
まず一つ目の理由として、フィルム選びに失敗しているケースが多いということです。防犯フィルムには厚みや耐久性、衝撃吸収能力の違いがあり、ホームセンターや通販サイトなどで手軽に購入できる安価なフィルムの中には、防犯性能がほとんど期待できないものも少なくありません。防犯効果を確実に得たい場合は、厚みが350ミクロン以上の強度の高い防犯フィルムや、防犯性能が認められている「CPマーク」の取得製品を選ぶ必要があります。
二つ目の理由は、施工方法の誤りによるものです。せっかく高性能な防犯フィルムを購入しても、貼り方が雑であったり、しっかり密着させていなかったりすると効果が激減します。フィルムと窓ガラスの間に気泡が入っていたり、端の部分がめくれている状態では、本来の防犯性能を発揮できません。そのため、正しい施工方法を理解した上で作業するか、専門業者に依頼することが重要になります。
実際、防犯フィルムが貼られている住宅では、窓からの侵入に5分以上かかることもあり、侵入者が諦めるケースも多いとされています。特に空き巣は「侵入に5分以上かかる家を嫌がる」というデータもあり、防犯フィルムを正しく使用すれば、大きな抑止効果を期待することが可能なのです。
つまり、防犯フィルムそのものが「意味ない」というのは誤解であり、正しい製品選びと施工を行えば、しっかりとした防犯効果を得られます。
次のセクションでは、防犯フィルムの効果を最大限に発揮させるための方法や、特に強力な「最強」と呼ばれる防犯フィルムについても詳しくご紹介していきます。
防犯フィルムの効果を最強レベルに高める方法
防犯フィルムの効果を最大限に高めるためには、まず防犯性能に優れた製品を選ぶことが重要です。また、その性能を十分発揮させるためには、正しく施工することが欠かせません。ここでは、効果的なフィルム選びのポイントや、防犯フィルム「最強」と呼ばれる高性能な製品について解説していきます。
まず、防犯フィルムを選ぶ際に重要なポイントから見ていきましょう。防犯性能を左右する大きなポイントは、「フィルムの厚さ」と「耐貫通性」です。一般的な防犯フィルムの厚さは200~350ミクロンですが、窓を破られにくくするためには350ミクロン以上の厚さが望ましいとされています。薄すぎるフィルムでは、ガラスが割れた後の侵入を防ぎきれない可能性があるため、注意が必要です。
また、耐貫通性(ガラスを破って侵入するのに必要な時間)は、防犯フィルムを選ぶ際の大きな基準になります。耐貫通性の高い防犯フィルムには「CPマーク」という認定マークが付いており、警察庁などが推奨している安心な製品の目安となっています。
次に、特に防犯効果が高いと評判の「最強」と呼ばれる防犯フィルムの特徴を紹介します。最強の防犯フィルムとされる製品は、厚みが400ミクロン以上あり、ハンマーやバールなどの道具を使っても簡単に貫通できない強度を持っています。また、多層構造で引き裂きにも強く、ガラス破片が脱落しないことで、侵入者が侵入を諦める確率を飛躍的に高めることが可能です。実際に、専門機関の試験でも高い評価を得ているものが多く、コストパフォーマンスの良さから一般家庭でも多く採用されています。
では、防犯フィルムを施工する際に気をつけるべきポイントを見ていきましょう。まず重要なのが、フィルムをガラス全面に隙間なく密着させることです。気泡が残ったり、フィルムの端が浮いたりすると、そこから破られやすくなり、防犯性能が著しく低下します。特に四隅やフィルムの端部分は、念入りに押しつけて貼り付けるようにしましょう。
また、防犯性能を高めるためには「ガラス全面」にフィルムを施工することがポイントです。一部分だけ施工した場合、貼られていない部分から簡単に割られてしまうことがあります。そのため、フィルムを貼る際には必ず窓全体をカバーするようにしましょう。
自分で施工する場合は特に、ガラスの汚れや油分をきれいに取り除いてから貼ることが大切です。フィルム専用の施工液を使い、ガラス表面を丁寧にクリーニングしてから貼りつけましょう。もし、施工に自信がない場合や、最強レベルの防犯フィルムを確実に施工したい場合は、専門業者への依頼を検検討するのもおすすめです。
このように、防犯フィルムの効果を最大限に引き出すためには、正しい選び方と施工方法を徹底することが重要です。次のセクションでは、防犯性能の指標となる「CPマーク」について、さらに詳しくご紹介していきますね。
CPマーク付き防犯フィルムとは?
「防犯フィルムを探していると『CPマーク』という言葉をよく目にするけど、実際何が違うの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?
ここでは、CPマークの意味や特徴、そして本当に効果があるのかを、詳しくわかりやすくお伝えしていきますね。
CPマークって一体なに?
CPマークとは、簡単に言うと「防犯性能が認められた製品だけに付けられる特別なマーク」のことなんです。
正式には「防犯性能の高い建物部品」として、警察庁や民間団体が協力して認定している制度なんですよ。
防犯フィルムの場合は「一定の時間、窓ガラスを破って侵入できない」という厳しい試験をクリアしたものだけが認められるため、マークが付いている製品なら安心感がグンと高まります。
つまり、CPマーク付き防犯フィルムは、品質・性能ともに信頼できる防犯フィルムということになります♪
CPマーク付き防犯フィルムのメリットは?
CPマークが付いている防犯フィルムの一番のメリットは、なんと言っても安心感です。
警察のお墨付きのフィルムを使えば、防犯性能が明確でわかりやすいのはもちろん、万が一の被害に遭ったときにも侵入されるまでの時間を稼げるため、被害を最小限に抑えることができます。
また、CPマーク付きの防犯フィルムを貼っている家には、専用ステッカーを貼れるものも多いんですよ。
このステッカーは防犯対策をしっかりしているという証明になるので、それだけでも空き巣が侵入を諦める確率が高くなるんです♪
CPマーク付き防犯フィルム、本当に意味あるの?
結論から言うと、CPマーク付き防犯フィルムは「意味がある」とはっきり言えます。
なぜなら、空き巣や侵入犯は、侵入に時間がかかる家を非常に嫌がるためです。CPマーク付きフィルムはガラスを割った後も容易に破れないように設計されているので、侵入を諦めさせる効果がとても高いんですよ。
特に女性の一人暮らしや、小さなお子さまがいるご家庭の場合には、安心して暮らすための効果的な防犯対策としておすすめできる製品です。
また、防犯性の高い製品を選ぶことで、ご自身やご家族の心理的な負担も軽減されるので、「ただのフィルム」以上の価値があると感じる方も多いようです♪
次のセクションでは、このCPマーク付き防犯フィルムを自分で施工する方法や、注意点についてもわかりやすくお伝えしていきますね!
CPマーク付き防犯フィルムを自分で施工する方法
CPマーク付き防犯フィルムは、防犯性能が高く専門業者に施工を依頼するイメージがありますが、実は自分でも施工することが可能です。
専門業者に頼むよりも施工費を節約できるため、コストを抑えたい方には特におすすめです。
自分で施工するために必要な道具や材料
まず、CPマーク付き防犯フィルムを自分で施工するには、以下の道具や材料が必要です。
- CPマーク付き防犯フィルム(購入時に寸法をしっかり確認)
- フィルム専用施工液(中性洗剤を水で薄めたもので代用可能)
- ゴム製のスキージー(気泡抜き用)
- カッター(余分なフィルムをカットするため)
- 霧吹きスプレーボトル(施工液を散布するため)
- 雑巾またはキッチンペーパー(ガラス清掃用)
これらはホームセンターやネット通販で手軽に購入することができます。
CPマーク付き防犯フィルムの施工手順とポイント
具体的な施工手順を順番に説明していきます。
①ガラス表面をきれいにする
施工前の窓ガラスにホコリや汚れが残っていると、フィルムが上手く貼れません。雑巾やキッチンペーパーでしっかりと汚れや油分を取り除いておきましょう。
②施工液を散布する
ガラス全体にまんべんなく施工液をスプレーします。施工液を多めに使用するとフィルムの位置調整がしやすくなります。
③フィルムを貼り付ける
施工液を散布したガラスに、フィルムを慎重に貼り付けていきます。空気が入らないように、中央から端に向かってスキージーで気泡を押し出しましょう。
④気泡を抜いて密着させる
端から丁寧に何度もスキージーを滑らせて、フィルムをしっかりと密着させていきます。この作業が防犯性能に大きく影響するため、丁寧に行いましょう。
⑤余分なフィルムをカットする
カッターを使って余分なフィルムを慎重にカットします。フィルムが完全に密着していることを確認し、端がめくれないように注意しましょう。
⑥最終チェック
施工後は24時間程度触れずに乾燥させます。完全に乾くまで窓の開閉は控えるようにしてください。
自分で施工する際の失敗を防ぐコツ
防犯フィルムの施工を失敗しないためには、次の3つのポイントを守りましょう。
- 施工時は2人以上で作業する
- 施工液を惜しまず使う
- 丁寧に気泡を抜く
特に大きな窓の場合は、1人で作業するのが難しいため、フィルムの位置決めや貼り付け作業は複数人で行うとスムーズです。
施工液が少ないと気泡が入りやすく、フィルムの位置調整が困難になります。たっぷりと施工液を使って貼り付けましょう。
気泡が残っていると、そこからフィルムが剥がれやすくなります。スキージーを使い、端まで気泡を完全に取り除くことがポイントです。
自分で施工すれば、業者に依頼するよりも大幅にコストダウンが可能です。正しい手順を理解して安全・安心な住まい作りを実践しましょう。
ホームセンターで防犯フィルムを購入するときのポイント
防犯フィルムは、専門業者だけでなく、近くのホームセンターでも手軽に購入することが可能です。しかし、ホームセンターで販売されている防犯フィルムは、製品の種類や性能に幅があり、選び方には注意が必要です。ここでは、ホームセンターで防犯フィルムを購入する際に知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。
ホームセンターで買える防犯フィルムの種類と特徴
ホームセンターで取り扱われている防犯フィルムは主に以下の2つのタイプがあります。
- 簡易タイプ(薄手のフィルム)
厚さが200ミクロン以下のものが多く、手頃な価格で気軽に購入できます。ただし、防犯性能は低めで、どちらかというと災害対策や飛散防止目的に使われることが多いです。 - 本格タイプ(厚手の防犯フィルム)
厚さが350ミクロン以上の防犯性能に優れたタイプで、一部のホームセンターではCPマーク付きのものも取り扱っています。強度があり空き巣対策として有効ですが、簡易タイプより価格が高めになります。
CPマーク付き防犯フィルムはホームセンターでも買える?
CPマーク付き防犯フィルムは、以前は専門店や通販のみで取り扱われていましたが、最近では一部の大型ホームセンターでも購入可能になってきています。ただし、小型のホームセンターや地域によっては置いていないこともあるため、事前に店舗へ確認すると安心です。
どうしても近くのホームセンターで見つからない場合は、ネット通販で注文する方法も検検討してみてください。
ホームセンターで購入時にチェックするポイント
ホームセンターで防犯フィルムを購入する際は、次のポイントをしっかりチェックしましょう。
- フィルムの厚みと性能表示
厚み350ミクロン以上で「防犯用途」「CPマーク付き」などの明記があるものを選ぶことが重要です。 - 対応サイズや寸法
自宅の窓ガラスにフィルムのサイズが合っているか、寸法を確認しましょう。大きすぎる場合はカットが必要、小さすぎる場合は防犯性能が落ちてしまうため注意が必要です。 - 必要な施工道具が揃っているか
ホームセンターなら施工に必要なスキージーや施工液、カッターなども一緒に購入できるため、忘れずにチェックしておきましょう。
ホームセンターで買うメリットと注意点
ホームセンターで防犯フィルムを買う最大のメリットは、製品を直接手に取って確認できることです。厚みや質感を確認したり、不安な点を店員さんにその場で質問したりできるため安心感があります。
しかし、店舗によって品揃えや価格が異なることがあるため、複数のホームセンターで比較検討すると、より良い製品を見つけることができます。また、在庫状況やサイズ展開が限られることもあるため、購入前にしっかり確認することをおすすめします。
防犯フィルムの施工価格の目安と費用を抑える方法
防犯フィルムを貼る際、性能と同じくらい気になるのが「施工価格」ですよね。施工価格は製品そのものの費用に加え、自分で施工するか業者に依頼するかによっても大きく変わります。ここでは、防犯フィルムの施工価格の相場や、少しでも費用を抑えるコツを詳しくお伝えします。
防犯フィルムの施工費用の相場ってどれくらい?
防犯フィルムの施工を専門業者に依頼した場合、窓1枚あたりの施工価格は、おおよそ以下のような相場になっています。
- 一般的な防犯フィルム(200~350ミクロン)
約8,000円〜12,000円程度(窓1枚あたり) - CPマーク付きの高性能フィルム(350ミクロン以上)
約15,000円〜25,000円程度(窓1枚あたり)
もちろん、窓のサイズや施工する枚数、業者によって価格は多少変動しますが、大まかな目安として参考にしてください。
防犯フィルムの施工費用が変動する理由とポイント
施工価格に差が出る理由は、主に以下の3つです。
- フィルム自体の性能や品質
性能が高い(厚い・CPマーク付き)フィルムほど高額になります。 - 施工する窓の大きさや枚数
大きい窓や枚数が多いほど費用が高くなるのはもちろんですが、まとめて施工すると割引が効く場合もあります。 - 施工の難易度や業者の技術料
特殊な窓や高所作業が必要な場合は価格が上がります。また、業者によって人件費に差があるため、相見積もりがおすすめです。
施工費用を抑える方法や工夫は?
防犯フィルムの施工費用を抑えたい場合、次の方法を試してみてください。
- 複数の業者で相見積もりを取る
業者によって価格が大きく異なるため、最低3社ほどの見積もりを比較するのがポイントです。 - まとめて施工する
窓1枚ずつ頼むよりも、まとめて施工すると割引される場合があるので、全体の施工を一度に依頼するとお得になります。 - フィルムを自分で購入し施工だけを依頼する
フィルムを自分で購入し、業者には施工だけを依頼することでコストを抑えることもできます。
自分で施工した場合と業者依頼の価格比較
例えば、1枚の窓にCPマーク付き防犯フィルムを貼る場合を比較してみましょう。
- 業者依頼の場合
フィルム代+施工代込みで約20,000円程度が相場。 - 自分で施工する場合
フィルム代のみ(約6,000円〜10,000円)+道具代(約1,000円〜3,000円)=7,000円〜13,000円程度。
このように、自分で施工すると、業者依頼に比べて約半額程度に費用を抑えられます。ただし、仕上がりの品質や手間、施工時間も考える必要がありますので、どちらがご自身に合っているかをじっくり検討してみてください。
防犯フィルムと防犯ガラスはどちらがおすすめ?
窓からの防犯対策を考えるとき、「防犯フィルム」と「防犯ガラス」のどちらがいいのか迷う方も多いのではないでしょうか?ここでは、それぞれの特徴や違い、メリット・デメリットを比較しながら、あなたのライフスタイルにぴったりな防犯対策を選ぶポイントを解説します。
防犯フィルムと防犯ガラスの特徴や違いは?
まず、それぞれの特徴を簡単におさらいしましょう。
- 防犯フィルムの特徴
防犯フィルムは既存の窓ガラスに後付けで貼ることで、ガラスを割られにくくするものです。施工が簡単で、コストも比較的抑えられるのがメリットです。 - 防犯ガラスの特徴
防犯ガラスは二枚のガラスの間に強靭なフィルムが挟み込まれている特殊ガラスで、ガラス自体が高強度に作られています。ガラスごと交換する必要があるため費用が高めですが、防犯性能や耐久性に非常に優れています。
防犯性能や耐久性はどちらが優秀?
防犯性能や耐久性という点では、「防犯ガラス」の方が優秀です。防犯ガラスは最初からガラス自体が強化されているため、割るのが非常に難しく、長期間安定した性能を維持します。また、CPマーク付きの防犯ガラスは防犯フィルムより侵入までの時間をさらに長引かせることができます。
一方で、防犯フィルムもCPマーク付きの厚みがあるタイプなら十分な防犯性能を発揮できますが、時間が経つにつれてフィルムの劣化や剥がれが起こる可能性があるため、定期的な貼り替えやメンテナンスが必要になります。
費用や施工面での比較・メリットデメリット
次に費用面や施工の手間を比較すると、以下のようになります。
- 防犯フィルムのメリット
費用が防犯ガラスより安く、施工が手軽にできるため、既存の窓を活かしたまま気軽に防犯対策が可能です。賃貸住宅でも手軽に取り入れやすいのも魅力です。 - 防犯フィルムのデメリット
経年劣化が起こりやすく、数年ごとに貼り替えが必要になることがあります。 - 防犯ガラスのメリット
耐久性が非常に高く、一度施工すれば長期的に安定した防犯効果を得られます。また、紫外線カットや断熱性能を備えたタイプも多く、省エネ効果も期待できます。 - 防犯ガラスのデメリット
費用が高く、ガラスごとの交換作業が必要になるため、大掛かりな施工が必要となります。賃貸住宅や集合住宅では設置が難しいこともあります。
結局どちらを選ぶべき?判断するためのポイント
それぞれにメリット・デメリットがあるため、最終的には以下のポイントを参考に決めましょう。
- コストを抑えて手軽に防犯対策をしたい方→ 防犯フィルム
- 長期間安定した防犯効果や耐久性を重視したい方→ 防犯ガラス
- 賃貸住宅など、大掛かりな施工が難しい環境の方→ 防犯フィルム
- 新築やリフォーム時など、予算に余裕がある方→ 防犯ガラス
ご自身のライフスタイルや住宅環境に合わせて、ベストな防犯対策を選んでくださいね。
防犯フィルムは意味ある!効果的な選び方まとめ
結論から言うと、防犯フィルムは決して「意味ない」ものではありません。むしろ、正しい製品を選び、正しく施工すれば、空き巣や不審者からの侵入を効果的に防ぐことができます。
防犯フィルムが「意味ない」と言われる主な理由は、「選び方を間違えていること」と「施工方法が不十分なこと」の2つでしたね。ホームセンターなどで売られている簡易的な薄手のフィルムでは防犯効果が得られにくいため、必ず350ミクロン以上の厚みがあり、できれば警察が認定した「CPマーク」付きの製品を選ぶことが重要です。
さらに、防犯効果を最大化するためには、施工時にも気泡を残さず丁寧に貼ることが大切です。施工に不安がある方は、専門業者に依頼するのも一つの手でしょう。
この記事では、防犯フィルムの効果やCPマークの意味、自分で施工するポイントやホームセンターでの購入方法、さらに防犯ガラスとの違いまで詳しくご紹介しました。あなたの生活環境や予算に合わせて、最適な防犯フィルムを選び、正しく施工して安全な住まいを実現しましょう。
「防犯フィルムは意味ない」と諦めてしまう前に、正しい知識と方法で、安心・安全な暮らしを手に入れてくださいね。